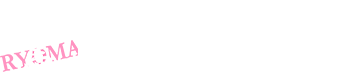お知らせNews
- HOME
- お知らせ
もう何年も、この文章はHPからはずしていました。が、この間の「親セミナー~いくつかの場面~」で話題に出て、復活してほしいというリクエストがありましたので、再掲することにいたしました。
十二歳の敗れざる青春へ
【エピソード1】
その知らせが届いた時、誰もが驚き、言葉を失った。
彼はクラスの誰よりもできた。彼が開成中に合格するのを疑う者はなかった。二番の子も三番の子も四番の子もみんな合格した。
しかし、彼だけは落ちた――。
僕は彼らと約束していた。「たとえどんな結果になろうと、必ず自分で報告に来い」と。その約束を守るために、彼がこっちに向かっているとの電話をお母さんからもらった。泣き崩れて発表会場の地面のコンクリートに拳と頭を打ちつけたという。
「先生――」「おう――」。明るく自然に。
「やられたか」「はい」気丈に答える。
「人間はなあ、やられた方が意味があることの方が多いんだぞ」
「……」
「他のみんなは合格した。おまえは入って当然なのに落ちた。ということは神様がおまえは開成に行くべきではないことを教えてくれたんだ。開成なんかじゃなく、おまえを選ぶことができた学校こそがおまえが幸せになる学校だという意味なんだ」。
唇をかみしめて、彼はじっと僕の目をみつめていた。
そこへ、開成に合格した同級生がご家族と共にお礼に来た。教務スタッフの対応で、それと悟った彼の目が泳いだ。
「あいつにちゃんとおめでとうって言って来い!」
「え?」
「友達が合格したんだ。祝福してやるのは当たり前じゃないか」僕は彼を連れ出した。
彼は歩み寄って、友達の手を両手でつかみ、そして叫んだ。
「おめでとう!おめでとう!おめでとう――!」
つかんだ両手を激しく振った拍子に、彼の両目から涙がほとぼり散った。
友人の家族はその場で泣き崩れた――。
「心がバラバラのままでした。でも、もしあの時彼を祝福することができず、隠れていたら、僕はもっとずっと不合格をひきずっていたように思います。あれが僕の原点でした。今、握手できた自分のこと、カッコ良かったと思います。先生はヒデェーけど――」
彼は海城高校に通い、学内で三番と下らなかったそうだ。そして、2005年春、東京大学理科Ⅰ類に合格した。
現在、忙しい学業の傍ら、ありがたいことに龍馬を手伝ってくれている。
【エピソード2】
その子は、一緒に受けた二人の友人と最後の合格発表に来ていた。今まで発表のあった学校はすべて落ちている。一緒にいる三人の中で自分が一番できないことも自覚していた。
「あったー!」一人の友人が顔をクシャクシャにして叫ぶ。
「ない……」もう一人が信じられないふうで、くずれ落ちそうに嗚咽する。
彼女自身は、自分の番号が当然ないことを確認しながら、涙が出ない自分にとまどいを覚えた。
一人になった帰りのバスの中……。
急にポロポロ涙が流れ出すのを彼女は止めることが出来なかった、と言う。
「二人は本当に頑張っていたから泣けたんだ。それに比べて、二人と同じ所を受けたいと思っただけで、自分は勉強なんて怠けていた。結果がどっちになったって、というより落ちるとわかっていたから、ちっとも悔しくなかった。だから、わたし一人だけなけなかったんだ」。
そう思った時、自分の情けなさに涙があふれてきた。
「両親に何度言われても、ただうるさいなあと思うだけで、口答えばかりして勉強しようとしなかった自分――。本当に心から両親にごめんなさい。と思いました」。
彼女は真剣に高校受験に取り組み、第一志望の県立千葉高校に合格。一橋大学を卒業した。
【エピソード3】
その時の僕はこの世で一番不幸な顔をしていた。
何人かの生徒の受験が思うようにいかなかった。周囲の期待とギャップのある結果に逃げ出したい気分になっていただけなのだろう。足を引っぱる俗物の同僚もいた。そいつを張り飛ばして八つ当たりもした(そいつは男のくせに泣きやがった)。
そんな時だった、家でも不機嫌な自分に女房が、
「違うでしょ、一番つらいのは落ちた生徒でしょ。あなたが今一番しなくちゃならないのは、その子たちを励ましてあげることなんじゃないの?自分の実績がどうの、カッコ悪いこと言わないで。先生なんじゃないの。合格させることが先生の仕事なの?私は違うと思う。これからがむしろ本当の先生の仕事なんじゃないの?」
典型的な亭主関白の自他共に認めている僕でも、この時の女房の言葉はこたえた。"きれいごと"と思われるかもしれないが。だが、今も僕はこの時の女房に感謝している。口では一度も伝えたことはないが――。
「結果にかかわらず、君たちは僕の自慢の生徒である」。
無責任かもしれないが、その時のつらい思いこそ、最高の結果なのかもしれない。自慢にはならないが、二十年もこの仕事をしていると、つらい思い出こそが彼らにも自分にも財産になっている気がする。
世間では、未だに小学生の塾通いはひどい、かわいそうなことだという認識がある。僕は全くそうは思わない。
目的を持って生きる青春を彼らが喜々として受け入れている現実がそこにあるからだ。甲子園で全力を尽くして敗れた者を笑う人間はいない。笑う奴らの人生こそ暗くて寂しいのだ。彼らは、たとえ味方のエラーで敗れても責めたりしない。「結果」が幸せなのではないことを知っているからだ。
受験生が百人いれば百のドラマがそこにある。彼らが手に入れるのは「ゴール」ではなく、「スタート」だ。「合格」は単純に幸せである。しかし、「不合格」という結果も彼らの青春には大きな財産である。どちらの結果であれ、彼らに敗北はない。彼らの青春を共有できる自分こそが幸せ者である。
【エピソード4】
次に紹介するお話は、中学受験に携わる人間としての僕の原点である。
筆者は、丸ごと受験生の母。もう二十年近くも前になるので、今とはいささか受験状況が異なる。"原文"をできるだけのまま載せたいので、先に説明をしておきます。
主人公は鹿児島ラ・サールを第一志望とする少年。当時は、開成中の入試は2月1が筆記、2月2日に面接、と二日間に渡っていた。巣鴨中は二次が2月3日で当日夕方合格発表。開成中の合格発表も同じく2月3日の3時くらいだった。そして、鹿児島ラ・サールだが、当時は2月20日過ぎの試験日程で、二日間の筆記試験だった。
〈2月7日〉
"蛇の生殺し"という言葉がありますが、現在の心境はまさにそのようなものです。
洋平は開成中に落ちました……
が、言葉に出さずとも、彼は面接で言われた言葉に一縷の望みを抱いているのです。そして又、母である私も……
……それは何か……
M先生(当時N研広報部長)の、「『開成に入ったら何がしたい?』と聞かれたら合格していることですから」と、攻玉社での面接模試で判定の際、洋平におっしゃった言葉です。
洋平に限らず、他の子ども達は受験前から知っていました。先生は又、公開模試の会場でも、あるいはN研開成受験父母会の席でもおっしゃいました。
一緒に受けた仲間が合格し、また自分が今まで一度とて遅れを取ったことのない子まで合格したこと、本人がこの試験で力を出せなかったのは事実ですが、納得のいかない負け方をしたことを悔いている上に、友達の中では一番長い面接時間であったこと、他の友達と質問内容が、一人だけ違っていたことなどから、自分はボーダーラインにいるのではないか、そしてM先生の言われたこと、過去の事例などから、もしかしたら繰り上がるのではいかという期待……それがわいて当然でしょう?
親にしても同じです。仕事に行くと、たとえ確実に連絡を取ってくださるといっても、もし家にかかってきたらどうしよう……。と考えると外出も出社もままならず、本当につらいです。本人にたとえ失敗しても受かるほどの力があればそれでいいのですが、諦め切れない受験をしてしまったのですから気にするなというほうが酷です。
試験の日、社会で時間を間違えて「3分の1は白紙」と言われたときは目の前が真っ暗……。友達があそこは○○○ここは△△△だなと言っているのを聞いて、書いて間違えれば納得もしようが、書かなかった上、自分にとってもは得意分野だったことがショックで、友達と肩を並べて歩きながら振り向いて私を見、小さく頭を振った時のあのさびしそうな。やるせなさそうな目、顔……忘れられません。
帰宅後、彼がしたことはなんと問題のやり直し……。私なら見たくもないのに、部屋にこもり、"同じ時間配分休みなし"で始めたときは、閉められた部屋の白いドアに向かって私はただ涙が出てたまりませんでした。
そして再び出てきた本人、算数のミスを見つけてしまい、社会はなんと40分足らずで解ききり、ほぼ正解。なんということでしょう。
開成発表の日、巣鴨の入試日……。暗いうち父親と私の三人で家を出ました。
「この時間ならこの季節でも北斗七星が見えるはずだ。あっ あった!すげぇでっかい!……」空に大きな七つ星……まったくきれいでした。
彼のその美しい余裕と、巣鴨は失敗すまいという気迫を感じました。
試験後、会場から出てきたいつもの洋平、自信を静かに腹にためた力強さでした。合格発表……。西日暮里4時半過ぎ、合格者は大きな封筒を持って校門を出てきます。
無いのです。
まわりの音が聞こえなくなって……こんなもの?……という感じ。他の友達の確認をして、電車の中でも妙な興奮状態でした。大塚についてすぐに見にいく気はせず、喫茶店へ……。つとめて明るい洋平……最初は他人事みたいな話しをしていたけど、
「そんなにいい子でいる事はない。言い訳でも、負け惜しみでもなんでもいいから言っちゃえ……出しちゃえ。」
と父親が言うと、たまらなくなったのでしょう。……うつむいて、ひざに顔をうずめるようにして泣き出すのです。必死に声を押し殺し、肩を震わせて……。
十二年の人生で、彼が流したおそらく初めての苦い涙……。親の方もくずれるのを抑えるのが必死でした。
どれほどの時間が経ったのでしょう、外はすっかり暗くなり、父親に、「そろそろ行こうよ……。ケーキ食べられないだろう?」と言われ、頭を上げた洋平、冷めた紅茶を一気に飲み干し、ケーキを口に放り込みました。
帰ってくる受験生とすれちがうのがいやだったのでしょう、
「こっちの方が近いよ……」
と言って別道を通ろうとします。黙ってついていきました。
門の所で江連君(洋平の大親友)と会う。洋平たちは気づかず掲示板へ向かった。江連君に洋平の番号があったことを聞く。彼に開成おめでとうと言っていたら洋平がやってきて二人で握手。合格通知をもらいに行く洋平に向かって暗い校庭中に響き渡る声で、
「川瀬! ラ・サール頑張れよ!」と江連君。
「おう!」と洋平。
後で主人に聞いた話……。
階段を昇りながら必死で歯をくいしばっていた洋平。ニコッと事務の人に笑いかけられ、涙があふれはじめ、
「川瀬君ですね。おめでとうございます。」
これでどっと涙だった。
〈2月17日〉
もうすでに神はレールを敷いてあるのではないかと思う。洋平の行く道は我々には見えていないだけで、ラ・サールの結果ももう決まっているように思う。
一週間、はっきりいって奇跡を待った。そのとき、ふと、受験勉強を始めた頃の日記を読んだ。そして何故我々が洋平を公立ではなく私立へやろうとしたのか……その原点をみつけ、思い出した。
私たちはその時、開成、ラ・サールといったトップ校のことは頭になかった。ただ、彼を"いい男"にしたい。スポーツと勉学と友情、そして豊富な経験に基づく教養を得させたいと……
そのためには公立のカリキュラム、学校生活では無理と判断したのだった。しかし、勉強を進めていくうちに、彼の努力で開成、ラ・サールを狙える力がついてきたということだ。目的がそこにあったのではなく、努力の結果がそこに見えてきたということか……
ここのところの自覚を忘れ、やはり開成病になっていたんだね。
「洋平止めよう。繰上げを待つなんて、あなたもお母さんもおかしかったね。どうかしてた。第一志望はラ・サールなんだもの。明日からまた頑張ろう」
……結果はもう用意されていると思う……
〈2月20日〉
朝、羽田へ送る。
どんな結果でも受けようという素直な気持ちと、諦めきれない親の見栄が絡みあって複雑な思いの私に比べて、静かな表情の洋平。
〈2月21日〉
朝、鹿児島よりの電話。
……パンツ忘れちゃった(自分で支度をしていったので)! 大笑いをする。大丈夫だ。
夜、鹿児島よりの電話。
……力を出せたと思う。
〈2月22日〉
朝、鹿児島よりの電話。
……パンツ買ったよ。元気で行ってくる。
〈2月23日〉
電報を受け取るため、早めに帰宅。
洋平は、英語〈当時、卒業生のためにあった中学準備講座)に行くかどうか迷っていた。
「あなたが自分の力をすべて出した……と、さわやかな思いがあるなら行きなさい。もし落ちていたとき、家にいたってことは自分に恥じることだし、卑怯だと思うよ」
「うん、わかった。N研へ行くよ」
と、靴を履きかけたときに電話……。N山先生からだった。合格の報だった。
鹿児島の先生が見て下さり、本部に連絡があったとのこと。M君(いっしょにラサールを受けた塾の同級生)にも早速知らせてあげた。父親にも知らせる。「よかったぁ……」の一言。
信じていながらも、正式の電報が来るまでの三時間は長く、落ち着かなかった。
教室へ電話。
「おめでとうございます。よかったですね。本部からすぐ連絡があったんですよ。今、安本先生がいらっしゃいますから代わります」
一方的にはずんだ事務の方の声に代わって先生は声を詰まらせて、
「終わりました……」
「川瀬が一番いい入試をしました。落ちて、苦しんで、そして最高の結果を出しました。何から何まで彼にとっては最高の経験。幸せな奴です」
先生のおっしゃった通りだと思います。このお言葉は、本人、我ら両親にとって最高のねぎらいとごほうびでした。
小さい頃から、努力すれば必ず自分のものとなる、と教えてきました。運動実技、遊びの技能、勉強……。しかし、中学入試は、努力は必ず報われるとは言い切れない余りにも大きな挑戦……。楽しく勉強していた彼の、2月3日以降の日々が本当の入試だったように思います。
子どもを励まし、指導してくださった先生方、友達の温かい友情、そして本人の努力……。これらが子どもを成長させてくれました。
この日々の思い出は切なくなるほど愛しい。子にも親にも素晴らしい宝物となるでしょう。
〈 後 記 〉
日ごろから事あるごとに記録している、我が家のノートに書き留めてあったものです。塾の父母会や学校説明会、お弁当のメニューまで。読み返すとまるで昨日の出来事のように思われます。
このようなドラマは中学入試をしたどのご家庭でもあることでしょう。事実、入学後の生徒を見ていると、どこかで傷ついた子どもが多いのです。思い出しても胸がしめつけられるのは親のみかもしれませんが、十二歳の子が、しっかりと青春したことは確かです。
そして今、私は後に続くいろんな子どもを青春にひきずりこんでいるところです。
川瀬洋平 母
【エピソード5】
先立って、「十二歳の敗れざる青春へ」に「蛇の生殺し」(エピソード4)を載せたいと川瀬に連絡したところ、彼から丁寧な手紙が届きました。第1章の最後にこの手紙を載せさせていただきます。たかが塾講師の幸せを伝えたかったからです。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
安本 満 先生
拝啓 新緑の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。
さて、大変遅くなりましたが、"蛇の生殺し"の原稿を送付いたします。
HPに載せる可能性があるとのことでしたので、勝手ながら電子化したもの(CD)も同封させていただきました。と申しますのも、母がこの原稿を作成した当時は、まだパソコンが普及しておらず、古いワードプロセッサを使って作成したものでしたので、電子化されたファイルがありませんでした。そこでこの機会に、僕が原稿を見ながら打ち込み、ワード形式に保存しなおしました。その際、若干、文章の体裁を整えておりますが、話の筋に影響は無いと思います。同封のCDに保存しておりますので、ご活用いただければ幸いです。なお、データー活用のCDは、ご自由にお使いになってください。
ところで、僕は、来春いよいよ東京で就職し、活動の本拠地を関東に移します。思い起こせば、現在僕のいる九州には、中・高・大+αで計15年間も住んでいたことになります。これまでの人生のうち、半分以上を両親と離れて生活してきました。しかし、遠く離れた両親にはいつも支えられていましたし、その温かい存在を忘れたことはありません。今回、"蛇の生殺し"を自分でパソコンに打ち込みながら、当時はよく分からなかった親の優しさというものを、つくづく感じました。また、受験を戦う小学生に接する安本先生のスタンスを思い出し、当時、カリスマだった先生のブレないポリシーの一端を改めて感じることができたように思います。安本先生に教わる子どもは幸せな奴です。
また朋友の江連ですが、ここ数年福岡で勤務していましたが、今春から東京に異動になりました。先々月のことですが、まだ福岡にいた江連夫婦を僕の妻と一緒に訪ね、一晩、四人で酒を飲み交わしました。17年前の同じ頃、別々の中学に進むことになった僕らは、まるで昨日のことのように思い出される当時の様子について、僕は江連のことを彼の嫁さんに、江連は僕のことを僕の嫁さんに伝えるようにして、熱く語り合いました。それは、とても幸せなひとときでした。江連本人は、相変わらず、頑張っているところを人に見せず結果だけを残すスタイルを貫きながら、前へ進んでいるようです。
20年前はまだ生意気で憎たらしい小僧だった僕らも、社会に出て数年がたち、それぞれ結婚し、今年で"三十"になります。中学受験を戦っていた当時、それぞれの偉大な親に支えられ"青春"していた僕らも、いまや一家の主として家庭を持ち、"而立"の年を迎えています。今後は、生涯の伴侶である妻とともに、それぞれの親に感謝しながら、"第二の青春"を追い求めたいと思っています。
わが青春の師、安本先生の、今後のご活躍を祈念しております。
最後に、言っても聞いてくださらないのは分かっていますが、言います。
どうか、お体ご自愛ください。
敬具
平成18年5月1日
川瀬 洋平